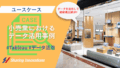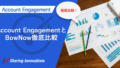Topics
【コラム】2025年の崖とは?DXで解決すべき課題と対策ポイント
2025年9月2日

- #コラム
2025年の崖問題とDXによる解決策を解説し、企業が直面する課題や対策ポイントをわかりやすくご紹介します。
日本の産業や経済に大きな影響を及ぼすとされる「2025年の崖」が注目を集めています。
システムの老朽化やIT人材不足が深刻化する中、多くの企業が業務のデジタル化やDX推進の重要性を認識しつつも、レガシーシステム刷新の遅れやデータの活用不足、運用保守コストの増大といった課題に直面しています。
「2025年の崖」を放置すれば、企業の競争力低下や事業継続リスクの高まり、最大12兆円規模の経済損失につながる恐れがあると指摘されています。
本記事では、その具体的なリスクや背景、成功に向けた対応策を詳しく解説します。DX戦略の見直しや新たなビジネスモデル構築に課題を感じている方にとって参考となる内容です。
経済産業省が警告する「2025年の崖」とは何か?
経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは、多くの日本企業が長年使い続けてきたレガシーシステムの老朽化・複雑化と、IT人材不足が深刻化することで、企業IT基盤が経済全体に大きな損失をもたらす可能性がある危機的状況を指します。2025年頃には、基幹システムのサポート終了やベンダー離れ、システムのブラックボックス化が進み、新規事業やサービスへの対応力が失われ、企業の競争力低下が懸念されています。
「2025年」が区切りとなる理由は、既存システムの運用や保守を担ってきたエンジニアの大量退職や、システム更新サイクルの限界が重なる時期だからです。対策が遅れれば、年間最大12兆円もの経済損失が発生すると予測されており、日本の産業競争力や社会基盤に深刻な影響を与える可能性があります。さらに、AIやクラウドといった新技術の活用やDX推進も停滞し、業務効率化やデータ活用による新規事業創出の機会を失うリスクも高まります。こうした状況を打開するには、レガシーシステム刷新や運用モデル改革など、抜本的なIT基盤の見直しが急務となっています。
「2025年の崖」による企業内システムの課題と問題点
「2025年の崖」に直面したとき、企業のITシステムにはさまざまな課題が表面化します。日本企業にはレガシーシステムが広く残り、ブラックボックス化、メンテナンス困難、人材不足、運用コストの増大、事業継続リスクの高まりといった問題が深刻です。これらは企業の競争力低下につながるだけでなく、デジタル技術を活用した新たなサービスやビジネスモデルの実現も阻害します。
・レガシーシステムの老朽化と複雑化
多くの企業で基幹システムが老朽化・複雑化し、全体像を把握できる人材が減少しています。内部構造がブラックボックス化し、機能追加や業務改革への柔軟な対応が困難な状況です。このため、DXで求められる業務効率化やデータ活用による変革が進まなくなっています。
・IT人材の不足と育成課題
2025年に向け、保守・運用を担ってきたベテランエンジニアの大量退職が予想され、IT人材不足はますます深刻化します。新技術やDX推進を担う若手人材の育成や、外部ベンダーとの連携体制の強化が急務となっていますが、十分に進んでいない企業も少なくありません。
・運用コスト増大と新規投資の停滞
老朽化したシステムの維持には多大なコストと労力がかかり、本来新規事業やデータ活用に充てるべき投資が滞ります。その結果、競争力強化やイノベーションの実現が後回しとなり、企業戦略の推進にも悪影響が及びます。
・事業継続リスクと社会全体への影響
レガシーシステムの障害時には復旧困難や情報漏洩、サービス停止などの重大リスクが発生します。特に基幹業務を担うシステムではその影響が大きく、企業のみならず業界全体や社会にも波及する恐れがあります。
・デジタル技術活用とDX推進の遅れ
AIやクラウド、データ活用といった先端技術の導入が進まず、新たな顧客体験やビジネスモデル創出への対応が遅れています。業務の柔軟性や経営判断の迅速化も難しくなり、DX全体の遅延が懸念されます。
・解決に向けた企業の取り組み
経営層はこの状況を認識しつつも、刷新コストやリスクの大きさから変革を躊躇しがちです。しかし2025年以降、「崖」が現実化すれば年間12兆円規模の損失が発生し、産業構造全体の再編も遅れます。これを防ぐには、IT基盤と業務プロセスの抜本的な見直し、新技術の積極導入、組織体制の強化が不可欠です。
また、課題分析に基づく対策モデルの策定、経営とIT部門の連携強化、外部の専門家やベンダーとの協力も効果的です。すでに移行やDX推進に成功した企業も現れつつあり、外部リソースの活用や業界横断の情報共有が、全体の解決への鍵となります。
今後、経営トップのリーダーシップ発揮と全社一丸の取り組みが、2025年の崖を乗り越えるために求められています。
なぜこれまで「2025年の崖」が放置されてきたのか
「2025年の崖」が長年放置されてきた背景には、企業内に根強く残る現状維持志向と、レガシーシステムの安定稼働への依存があります。長期間運用してきた基幹システムは業務に深く組み込まれており、抜本的な刷新には多大なコストとリスクを伴うと認識され、積極的な改善が後回しにされてきました。加えて、大規模な移行が事業活動に及ぼす影響への懸念も、経営層の意思決定を鈍らせていました。
また、経営層がITの持つ経営戦略上の重要性を十分に認識せず、IT部門への丸投げやブラックボックス化が進行、全社的な課題として問題が共有されず、IT人材の育成や新技術への投資も停滞しました。
一方で、外部ベンダーとの関係も現状維持に留まり、保守や部分的な改修が中心となり、システム全体の抜本改革が進まない構造となっていました。特に、複雑な業務要件や長年蓄積されたデータ移行の難しさが課題として放置され、刷新へのハードルが高まっていました。
産業全体としても、DXやAI、クラウドといった新技術の価値認識が遅れたことも背景にあります。既存システムへの過度な依存、変化への抵抗感、そしてコスト負担への懸念が、変革への第一歩を阻んできたと言えます。
さらに、現場レベルでも「効率化や新規事業には刷新が必要」と理解しつつ、リスクやコスト、経営の後ろ向き姿勢が障壁となり、DX推進に踏み出せない状況が続いてきました。
「2025年の崖」を解決するためにすべきこととは?

「2025年の崖」を克服するために企業がまず着手すべきは、レガシーシステムからの脱却と基幹システム刷新です。業務全体を俯瞰し、現状課題やリスクを整理したうえで、経営戦略と直結する形でのデジタルトランスフォーメーション(DX)推進が求められます。
特に以下のステップでの取り組みが重要です。
【DX推進の基本ロードマップ】
- 現状分析と課題の明確化
- 経営戦略と連動したDX方針の策定
- IT人材の育成と社内マインドセット変革
- 先進デジタル技術の積極導入
- セキュリティ対策の強化
- 段階的な移行計画の策定と実行
- 外部ベンダー・専門家の活用
– システム構造、運用実態、業務プロセスの可視化と評価
– 事業方針・競争力強化と整合するIT戦略の明確化
– DX推進への意識改革、リスキリング、デジタル文化の醸成
– AI、クラウド、ビッグデータ、ローコード等の活用
– クラウド・分散システムへの移行に伴う情報セキュリティの強化
– 業務影響やコストを考慮したスモールスタートと継続的改善
– システム刷新経験のあるコンサルタントやSIerとの協働
また、部門横断型のプロジェクト体制の確立や、データ活用を前提とした業務プロセス改革も不可欠です。全社でデータを価値創出に活かせる仕組みを整えることで、生産性向上と新事業創出につながります。
加えて、社内だけでの対応が困難な場合は、外部支援を積極活用する姿勢も求められます。クラウド、AI、運用効率化モデルなどを実装・運用するための外部ノウハウの活用が、コスト最適化と移行成功のカギを握ります。
最後に、最も重要なのは経営層による「変革への明確な意思決定」と「リーダーシップ発揮」です。これなくして、全社一丸のDX推進と「2025年の崖」克服は実現しません。
まとめ
「2025年の崖」は日本経済や企業の未来に大きな影響を及ぼす重要な課題です。レガシーシステムの老朽化、IT人材の不足、DXの遅れは、企業の競争力や事業継続、経営全体に深刻なリスクをもたらします。今こそシステム刷新やデジタル技術導入、業務変革の取り組みを本格的に開始すべきタイミングです。
今後の経営戦略や事業価値向上のためにも、現状分析と具体的な対策が欠かせません。DX推進に向けた相談や支援は専門パートナーに依頼するのが有効です。ぜひ早めのアクションをご検討ください。
DX推進についてのご相談はぜひ Sharing Innovationsへ
DXの推進や社内システム構築、業務プロセスの刷新、レガシーシステム対応に課題をお持ちの企業様向けにご相談を受け付けています。
複雑なシステム運用やIT人材の確保、最新デジタル技術の導入、DX戦略立案の支援など、さまざまな事業課題に対応できる支援体制を整えています。自社の現状把握や課題の棚卸し、具体的な導入・開発計画の策定、実行支援まで幅広くサポート可能です。
少しでもDXに関して悩みや不安をお持ちの企業様は、資料請求やお問い合わせも随時承っています。現状分析から課題解決のための最適なご提案まで、お気軽にご相談ください。
※文中に記載されている会社名、商品名、サービス名は各社の商標または、登録商標です。